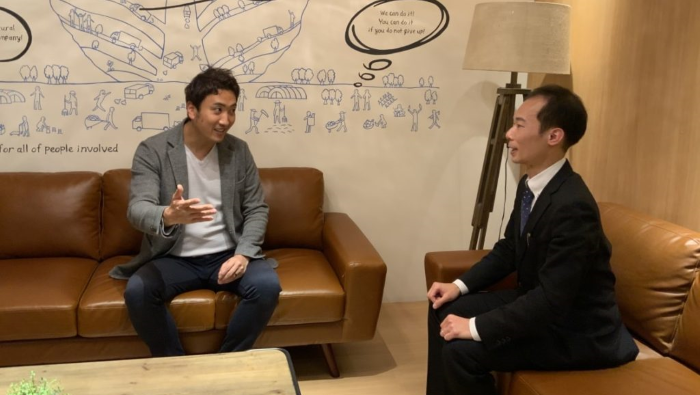PR活動により認知度を拡大し
世の中への価値提供を加速したい
農家と消費者をつなぎ合わせ、一つの架け橋となって日本全国に野菜と元気を届ける、
株式会社フードサプライ。
産直品を低リスクで購買したいお客さまと、長期にわたる安定した契約を望む農家。
この両者のあいだを取り持ち、お客さまでも産直野菜を仕入れることが可能な体制を提供しているのが、フードサプライです。
今回は同社、代表取締役 竹川 敦史様、 商品管理本部 プロジェクト推進特命担当係長 向井 昇様 に
お話を伺いました。

「ネタもと」導入前の課題や悩み
当社は「社会問題を解決したい」という強い思いがある事業を行っています。
農業や青果業界は、誇るべき仕事なのに、そのように見えていない。
その存在価値をもっと訴えていくために、世の中に広く農業や青果業界の「今」を知ってもらいたいという思いがありました。
また、当社の事業モデルは、コロナ禍では社会貢献の一面も持っています。
こういった面から「もっとブランディングをしていくべき」と感じていました。
実は、「ネタもと」を活用する前の2020年3月~5月の3か月間、広報活動に注力し、その時に約50件くらいのメディアに掲載されたんです。
その経験からメディアについて自分たちなりに学びましたし、マスメディアに出ることの効力を知りましたね(竹川社長)
「ネタもと」を選んだ理由
自社の事業を広く知ってもらうことができれば、「こんなことをやっているのか」とお役に立てることがあるかもしれない。それでPR活動をするべきだと思ったんです。
「ネタもと」を選んだのは、自社の広報活動で「メディアの効果ってすごいよね。 独自でやってこれなら、専門家と組んだらもっとすごくなりそうだよね」ということで、いくつかの会社と契約しました。
そのうちの一社が「ネタもと」でした。
「ネタもと」を活用した広報活動を始める前から、テレビの影響力は感じていました。
メディアの可能性を感じて、さらにチャネルを増やそう、と取り組んだのが「ネタもと」でした(竹川社長)
実際の取り組みや工夫したこと
まずは、「ネタもと」に備わっている「リクエスト」を大いに活用しました。
毎日メディアから届く「取材リクエスト」のテーマの中から、自社の事業に関わるネタ募集を逐一チェックし、もれなく情報を出すようにしていました。
また一見、自社に関係のないようなものでも、どのように情報を加工すれば「エントリー」できる情報が作れるかを、社長の指導のもとで相当考えました(向井様)
それと、プレスリリースの作成・配信ですね。
なぜトピックスとして取り上げてもらえたのか?
なぜ目に留まらなかったのか?内容・タイトル・日時・何が要因なのかを、私と向井とで協議しながら次回の情報発信のために準備を進めています(竹川社長)
社長からの指導で、メディアへの対応は「スピード重視」。即レスを徹底しました。
対応に時間を要するものは「〇日までにお戻しします!」と初動を早くするように心がけています(向井様)
掲載された媒体の一例
・通販新聞
・news every.
・めざましテレビ
・農経新聞 など
ネタもとを活用して得られたこと
社内的には、コロナ禍で売上げが落ちてしまっても、メディアに取り上げられることで従業員のモチベーションもあがりました。
社外的には、色んなところで「あの記事見たよ」と声をかけられ、色んな人の目に触れられているのだと実感しています。
また、ドライブスルー八百屋の利用者数や、HPのPV数が激増しました。※参考(ドライブスルー八百屋に6万人来場、HPは200万PV)
「ネタもと」を活用したことで、自分たちがこれまで取り組んできたPR活動について、答え合わせができたと思っています。
ネタもとさんは、いわば「広報の教科書」であり、いろんなことを教えてくれる。
しかし、活用するかどうかは、自分たち次第。導入しただけでは、効果は出ません。
当社では強い思いをもって事業に取り組んでおり、それを世に広げていくときに「ネタもと」が役に立ちました。
「ネタもと」で学んだことを、自社に持ち帰り、自社なりに考えて工夫することが、成功につながると思います。
広報PR活動において何より大事なのは、何を活用するかよりも、自社の事業を世に伝えたい、広げていきたい、という企業側の熱意だと思っています(竹川社長)

どのような企業に「ネタもと」を勧めたいか
新たに広報をはじめる企業様や、広報ご担当者が育っていない企業様などは、加入すべきだと思います。
私たちは、ある程度行動をしてから、ネタもとを使い始めましたが、『広報の基本』は、絶対に勉強したほうがいい。
広報をあまりやったことがない企業であれば、ネタもとさんのセミナー・勉強会はすべて参加したほうがよいと思いますよ(竹川社長)
今後のさらなる目標
今後も、消費者の皆様に満足していただき、結果としてメディアの方々に注目していただけるよう 、さまざまな取り組みをしていきたいですね。
そして、このコロナ禍でも業界の価値をより多くの方に知っていただけるように盛り上げていきたいと思っています(竹川社長)
” 野菜の新しい流通 “をつくれば、日本はもっと元気になる。
この信念を胸に、野菜の価値を高め、農家のみなさんの所得を上げ、そして安心安全な商品をより安く食卓に届けるために「流通革命」に挑み続ける竹川代表。
今年1月、再び緊急事態宣言がなされ、飲食店へ時短要請が出された際は、
農家、製造業、物流業を守るために、いち早く「ドライブスルー八百屋」を再開。
混雑したスーパーのレジに並んだり、大勢の人が触った野菜を買うのに抵抗がある消費者に対しては、不安を解決する策として、外食向けに販売予定だった野菜をお得に詰め合わせ「もったいない野菜セット」として販売。
常に「社会問題を解決する」ことに全力を傾ける株式会社フードサプライ。同社の社会的価値の高い取り組みは、「広報PR活動」という手段により、今後さらに広がっていくことでしょう。
お忙しい中、取材にご協力いただきました竹川代表、向井様、ありがとうございました。
参考:株式会社フードサプライ様 社員200名( 2021年2月現在)